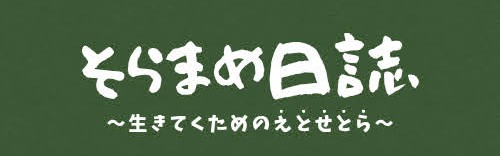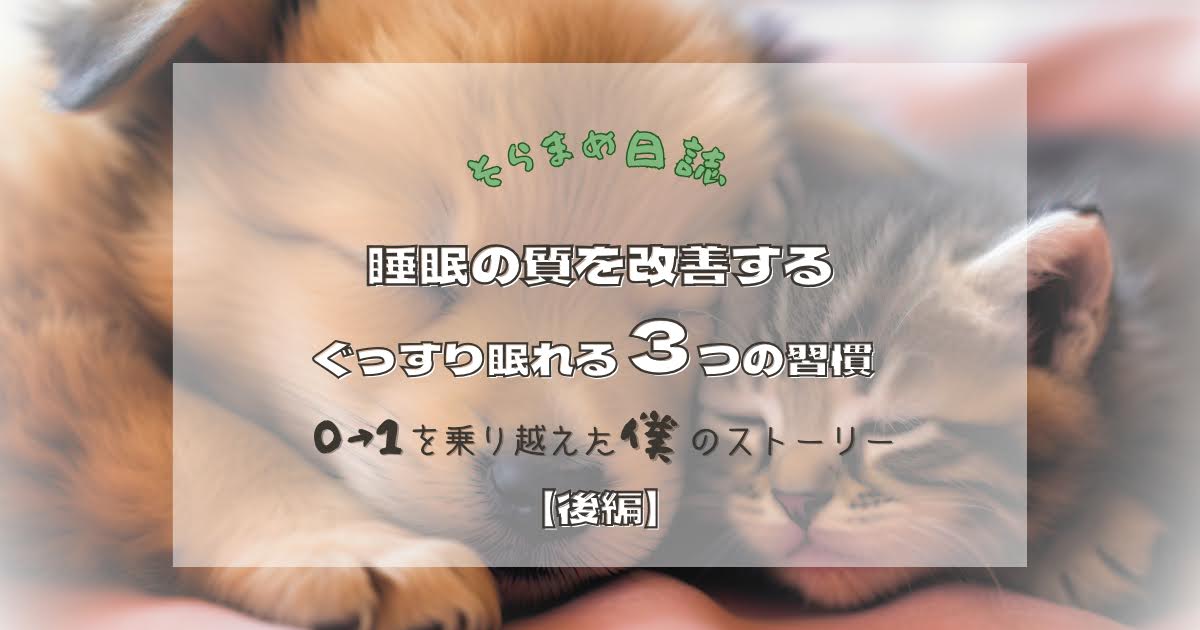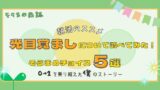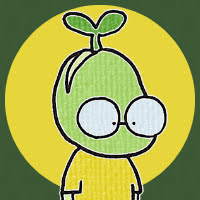
この記事は【前編】の続きです。
前編をまだ読んでいない方はコチラからどうぞ
前編では、
時間のコントロール や スマホとの距離感 といった、睡眠のベースづくり に注目しました。
後編では、
・・・といった メンタルケア や セルフマネジメントの側面 に深掘りしていきます。
寝室の環境を落ち着く空間に整える(温度・光・音)

「眠れない原因は、もしかしたら 自分の部屋 にあるのかも・・・」
そのように思ったことはありませんか?
眠りに入りやすくなるかどうかは、寝る場所の雰囲気 に左右されることも多いんです。
寝室が 心を緩める空間 であるべき理由
人間の脳には、場所と行動を結びつけて覚える性質があります。
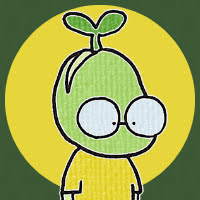
例をあげてみます。
- デスクに座ると、集中モードに入る
- カフェに行くと、気持ちが切り替わる
- ソファに寝そべると、だんだん力が抜けてくる

人によってその感覚が異なると思います。
寝室についても、同じことが言えます。
つまり、寝室を自分にとって くつろげる快適な空間 にすれば、脳は自然と「ココにいるということは・・・眠る時間なのね」と認識してくれるようになるんです。
「整った部屋」より「落ち着ける部屋」を目指す
睡眠改善というと、「生活感をなくして整った部屋にすればいい」と思う人もいると思います。
僕の考えは違います。
見た目 よりも 心が落ち着く空間 をつくることが大事 だと僕は思っています。
なぜこのように思うかというと、人によって 安心できる空気感 が異なるためです。
まずは、自分にとっての落ち着ける要素を見つけることがカギだと思います。

僕の落ち着く環境は、無音・狭い・毛布素材に囲まれる・・・といった感じです。
睡眠の質が上がる寝室づくり|4つのポイント
ここからは、僕自身が試して「これは良い!」と感じた具体的な環境調整のポイントをご紹介します。
① 照明|夕方のような光にする
白い蛍光灯ではなく、オレンジ寄りの電球色を選びます。
間接照明や、調光できるライトもおすすめです。
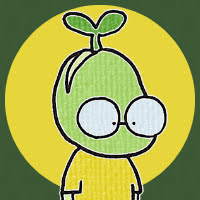
僕の場合、オレンジ色の照明の喫茶店では何故か眠くなります。
ポイント
暖色系の光は、リラックスできます。
② 音|静かすぎるのが落ち着かない時の自然音
僕の場合、無音の空間がとにかく好きなのですが、 無音が逆にストレスになる人は、小さな環境音を流してみてはどうでしょうか?
- 雨の音や波の音、焚き火の音など
- 扇風機などの電化製品音もハマる人にはおすすめ
ポイント
リズムのある繰り返し音が脳に心地よく働きかけます。
③ 温度・湿度|身体がリラックスできる環境に整える
「少しひんやり」「呼吸がラク」くらいがベストです。

僕の場合は少し肌寒い環境で、もこもこ毛布にくるまって寝るのが快適なのさ!
ポイント
温度差は眠りを妨げる大敵。寝具の調整も忘れずに!
④ 香り|いつもの匂いでリラックススイッチON
ほんのり漂う自然な香りに癒される人は多いと思います。
ラベンダーやヒノキの香りをすすめてくる友人がいて、確かに、香水とは違う効果がある印象を受けました。

かくいう僕は、無臭空間じゃないと落ち着かないけどね・・・
ポイント
香りの記憶が 入眠スイッチ になる(アンカー効果)
まずは実験してみること
ここで大事なのは、「正解の形」を目指すことではなく、自分にとって心地いい睡眠スイッチを探していく姿勢です。
僕の場合は、夜中に寝ながら起きてしまう癖があるので、「寝る直前に気持ちが刺激されすぎないように・・・」と視覚・音・匂いによる刺激が少ない空間に整えるようにしています。
「なんかこの照明、落ち着くかも」「この音、安らぐ・・・」
そんな小さな感覚の積み重ねが、結果的に深い眠りにつながる土台になってくれます。
朝起きた瞬間のダルさを少しでも減らしたい場合、寝起き環境を整えるのも効果的です。
僕が最近リサーチした「光目覚まし」は、体内時計の調整をサポートしてくれるアイテムとして注目されています!
カフェインやアルコールの摂取タイミングに注意

「寝る前のコーヒーやお酒って、ダメなの?」
よく耳にする疑問です。
意外と曖昧なままになっている疑問ですよね。
実はこの2つ、使い方次第で睡眠の味方にも敵にもなるんです。
カフェインは「午後○時まで」と決めてみる
カフェインには、脳を覚醒させる作用があります。
集中力UPや眠気覚ましにはうってつけとよく言われている所以です。
更にカフェインには、身体の中に長く残りやすいという特徴があります。

かくいう僕は、カフェインで眠れなくなったことないけどね・・・
アルコールが睡眠サイクルに及ぼす影響
アルコールは 眠れるけど、眠りが浅くなる ・・・
お酒を飲むと、一瞬で眠くなるという話を聞いたことがあります。
これは 睡眠薬的なノックダウン に近い状態で、眠りの質はあまり良くないんです。
これは、アルコールが深い眠り(ノンレム睡眠)を妨げてしまうからです。
アルコールが睡眠サイクルに及ぼす影響
すべてをやめる必要はありません。
むしろ「眠りを邪魔しない使い方」を知っておくことのほうが重要です。
🔹 カフェインとの付き合い方
🔹 アルコールとの付き合い方
リラックスできる寝る前のルーティンを作る

あなたは、「この行動をすると、自然と眠くなる」というルーティンを持っていますか?
もしまだなければ、これから紹介する考え方を少し取り入れてみてください。
入眠スイッチ を自分で作ることができるかもしれません。
実は、僕は昔から「寝つきが悪い」ということがほとんどありませんでした。

むしろいつでもどこでも寝られるほうかも・・・
でもその一方で、夜中に突然起きて寝たまま行動してしまうことがあります。
これってもしかすると、深いところにある無意識が関係しているのかも?
そんな風に考えるようになって、「寝る前の過ごし方」をちょっと意識し、変えてみました。
脳には習慣をトリガーにする力がある
心理学には アンカリング という言葉があります。
これは、ある行動や出来事が、自動的に特定の感情や反応を引き起こす仕組みのことです。
- 特定の香りを嗅ぐと、小学校の教室を思い出す
- この音楽を聴くと、あの頃の気持ちがよみがえる
- マグカップを手にすると、なぜか落ち着く
このような経験、あなたにもありませんか?
この アンカー効果 は、眠るための夜ルーティンづくりにも応用できるんです。
僕の場合、子どもの頃に家で犬を飼っていて、いつも同じ布団で、同じ枕で寝てました。
今は動物を飼っていないので、当たり前ですがひとりぼっちで眠っています。
そこで、動物のもふもふに近い毛布を犬サイズに丸めて横に置くと、眠りモードに突入できるわけです。
「よく眠れてるけど、もっと整えたい」あなたへ
正直に言うと、僕は今でも「眠れない!」と悩むことがほとんどありません。
そのため、スマホをわざと長く使って眠れなくなる感覚を体感してみたり、夜ふかししてみて翌日の思考力の低下をチェックしてみたり・・・
このような視点で、たまに睡眠を研究しています。
そんなことから思ったことは・・・
「眠れること」と「質の高い眠り」は違う
・・・ということです。
ぐっすり眠れているようで、心や身体がちゃんと休まっていないこともあります。
バタバタ忙しく駆け回る夢を見ると、朝起きたとき、妙に疲れたりしていることもあります。
眠る前の時間をどう使うかによって、睡眠の質は変わり、次の日のコンディションに大きく影響してきます。
「眠れない夜」は無理に寝ようとしない

「明日早いのに・・・」
「また眠れなかったらどうしよう・・・」
このように思えば思う程、なぜか眠れなくなる・・・なんてことがあります。
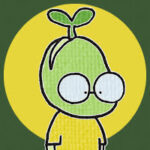
僕の父がそうです。
そんな時は、無理に寝ようとしないことが良いみたいです。
「眠れない=悪いこと」と思うともっと眠れなくなる
人間の脳はとても敏感で、「眠らなきゃ!」と思えば思う程、脳が戦闘モードに入ってしまう性質にあります。
つまり、眠ろうと努力すること自体が、逆に眠りを遠ざける原因になってしまうこともあるんです。
僕の父の小さな実験|眠くなる音楽を、眠る目的で聴かない
なかなか寝付けない父は、睡眠用の音楽を聴いていた時期がありました。
でも、寝るために音楽を聴くと、「眠れなかったらどうしよう・・・」と気にしてしまって、逆に緊張して眠れなくなってしまったり・・・という新たな悩みが出てきました。
そこである時からは、
「この曲、夜に聞くと落ち着くな〜」
「別に眠らなくても、気持ちがゆるめばOK」
というように、音楽の目的を癒しに変えてみたのです。
そうすると、何となくうとうとモードに突入し、眠りやすい落ち着いた環境がひとつ整ったという気持ちになったようです。
おわりに|眠れることは、「立ち上がる力」につながる
眠りは、ただ身体を休めるだけのものではありません。
日中に受けたストレスをリセットしたり、次の日のあなたをつくるための、 静かな準備時間 でもあります。
「よく眠れたな」と感じた朝は、心が軽く、ちょっとだけ前向きになれる気がしませんか?
僕自身は、睡眠に大きな悩みを抱えたことはありません。
でも、だからこそ──
眠れない夜の辛さ も、眠れることのありがたさ も、
ちゃんと想像しながら書きたいと思ってこの記事をまとめてきました。
完璧な眠りを目指す必要はありません。
できることを、できるタイミングで、少しずつ試してみる。
それだけで、眠る力はちゃんと取り戻せます。
そしてそれはきっと、
あなたが毎日を立ち上がる力にもつながっていくはずです。
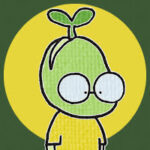
ぐっすり眠れますように。
※ 本記事は医療情報ではなく、日常生活に役立つセルフケアを目的とした内容です。
心身の不調が続く場合は、専門の医療機関にご相談ください。